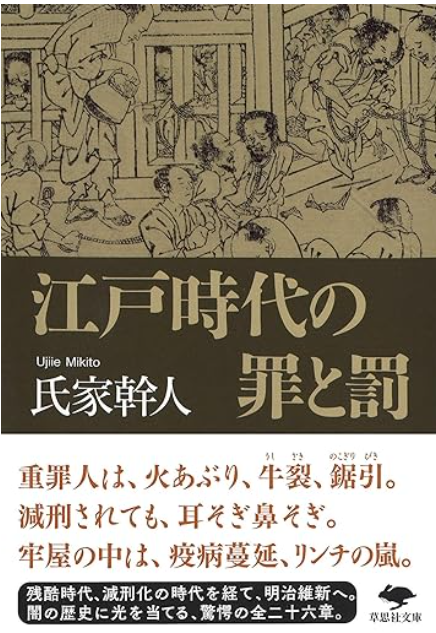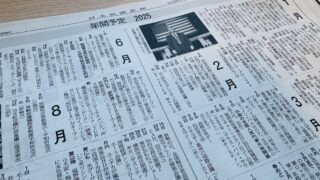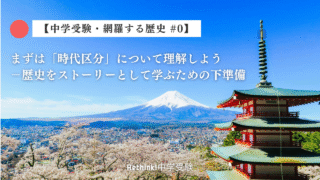こんにちは!
今回は江戸時代の政治や法律に出てくる重要なキーワード、「公事方御定書(くじかたおさだめがき)」について解説します。
中学入試でもよく出てくるポイントなので、しっかりおさえておきましょう!
公事方御定書ってどんなもの?
公事方御定書とは、簡単に言うと「江戸時代の裁判や刑罰のルールブック」です。
- いつ作られた?:1742年(寛保2年):江戸時代中期
- 誰が作った? :8代将軍・徳川吉宗
- どんな内容? :裁判での判断基準やどんな罪にどんな罰を与えるかをくわしく決めたもの。
なぜ作られたの?
なぜ作られたのかを知るためには、江戸時代の初めの頃の裁判事情を知る必要があります。
江戸時代の初めの頃は、裁判のやり方や罰の決め方の決まりがなく、奉行(今でいう裁判官のような役人)が各々自分で考えて判断するしかなかったんです。要は、裁判や罰の基準がバラバラということです。
でも、それだと「人によって裁きが違う!」ということになり、トラブルの元になったりしてしまっていたわけです。
そこで第8代将軍の徳川吉宗はこう思いました。
「全国で統一された裁判ルールを作ろう!」
裁判の基準を統一して決めることによって、みんなが公平な裁判を受けられるようにしようと思ったわけです。
ちなみに、この公事方御定書は、徳川吉宗の「享保の改革」で行った施策の一つです。(享保の改革は幕府の財政を立て直し・人々のくらしの安定を目標とした改革です。)
公事方御定書の内容は?
さて、徳川吉宗の発案によって作られた公事方御定書ですが、内容としては上下2巻に分かれています。
| 巻 | 内容 |
|---|---|
| 上巻 | 司法・警察に関する基本法令81条。 |
| 下巻 | 犯罪と罰についての判例103条。 |
下巻は「御定書百箇条(おさだめがきひゃっかじょう)」と呼ぶことも多いです。この下巻では、実際の判決(=判例)をまとめることで、役人が「前はどうだったか」を参考にできるようにしました。すなわち、前例を参照することによって「前と違う!」という不公平をなくしたわけです。
公事方御定書をはじめとする江戸時代の司法に関しては以下の書籍がオススメです。興味のある方はぜひ読んでみましょう。
『江戸時代の罪と罰』
どうして大事なの?
公事方御定書がなぜ大事なのかというと、以下の3点が挙げられます。
- 江戸時代の法のしくみが整った大きなきっかけになった
- 裁判の公平さ・正しさが守られるようになった
- 現代の「刑法」や「裁判制度」にもつながる考え方がここにある
また、中学受験という視点で見ても、江戸の改革の一つとして「目安箱」「上米の制」と並んで吉宗の改革ポイントとしてよく出題されます。実際の出題例を次の章で見てみましょう!
「公事方御定書」の出題例(中学入試過去問)
佼成学園中学校 2022年度大問2
以下のA~Cに当てはまる語句を漢字で答えなさい。
( A )の改革を行った人物は8代将軍( B )で、自ら幕政の指導にあたりました。大岡忠相(おおおか ただすけ)を登用し、裁判が公平に行われるように( C )を制定した。(佼成学園2022・改題)
答えは、A:享保、B:徳川吉宗、C:公事方御定書。
まとめ
では最後に、簡単にまとめておきましょう。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| いつ作られた? | 1742年 |
| 誰が作った? | 徳川吉宗 |
| どんなものを作った? | 裁判・刑罰のルールと判例 |
| なぜ作った? | 裁判のやり方を全国で統一するため |
| どんな構成? | 上巻=司法ルール、下巻=判例 |
.
ではでは、今回はこのあたりで。
最後まで読んで下さり、ありがとうございました!